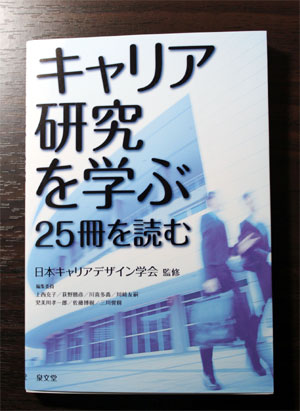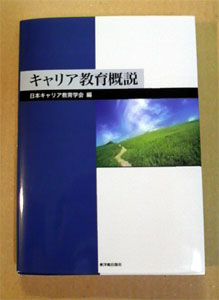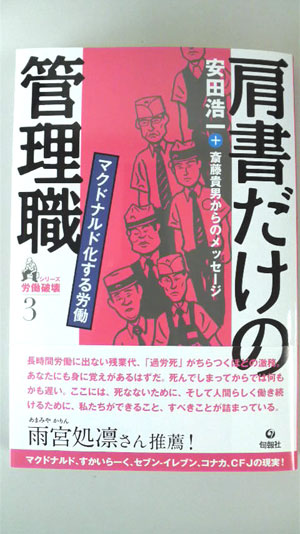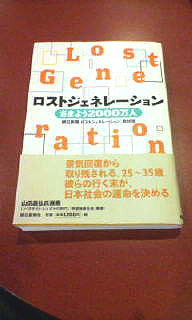石井京子 2010 人材紹介のプロが作った発達障害の人の就活ノート 弘文堂
http://amzn.to/bwVWCK
著者の石井氏は、障害者雇用に携わってきた人物。
まずは基本的なことが書かれている
たとえば、p7~8をまとめると
以下のことなど。
・発達障害という診断名だけでは障害者雇用の対象とはならない。療育手帳または精神障害保健福祉手帳を取得すると障害者雇用の対象として扱われる。
・療育手帳の取得となるかどうかの判定はIQなどを測定して行われる。判定基準は自治体によって若干の差がある。発達障害の診断を受けていて就労が続かないなど社会生活上の困難がある場合は、基準を引き下げて交付する自治体もある。
・精神障害者保健福祉手帳は精神科医の診断が必要だが、広汎性発達障害という分類で手帳が交付されるかどうかは、都道府県によって異なる。
・手帳を取得することは本人にとって大きな決断であるが、ひとつだけ言えるのは、障害者手帳を持っているかどうかは、"本人が申告"しないと雇用者も周囲も分からないということ。
特に最後の点なんかは、当事者の中には「勝手に知られるのはいやだから手帳を取得しない」という誤解のある人が一定数いることを物語っていると思われる。実際に当事者との相談場面でも出てくる。
以降は主に発達障害の場合でも、障害者手帳を取得した場合に、どのような点がポイントになるかが書いてある。たとえばp25は下記の点。
障害者雇用での面接で合格する人の共通点。1)障害を受容していること 2)障害の特定の分析ができている 3)希望する配慮を具体的に説明できる 4)過去の職場での不適応経験もきちんと説明できる
また、コラムも充実している。
学校は卒業したけど社会参加が難しい18歳以上の人向けに社会性を教える学校の実践や、自閉症の強みを引き出す企業の例、当事者が語るニーズ、発達障害がある子どもたちに療育を行っている株式会社など多角的に書かれている。
個人的には、発達障害がある子どもたちに療育を行っている株式会社のコラムが最も印象的だった。具体的には下記。
「最後に『他者と一緒に過ごすことを楽しめる』、これがもっとも大事なのかもしれません(中略)この気持ちが育っているからこそ、先生に教わったり、周りの人が行っていることを真似たりしながらソーシャルスキルを学び、使いこなしていくわけです(p28-29)」
石井氏は最後のコラムで
下記のようにまとめている。
「人事業務の中で障害者雇用および雇用管理の重要性がうたわれている昨今、発達障害をもつ方への理解と合理的配慮、そして職場でおきやすい問題への対応も含めた雇用管理を実践することは、今後の人事担当者のスキルとして高く評価できることだと思います(p172)」
この指摘は強調してもしすぎることはないと思う。